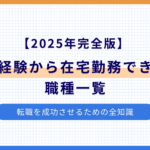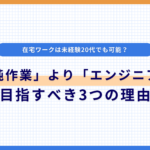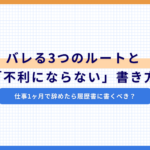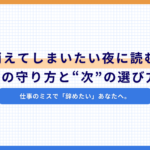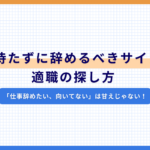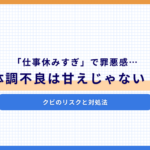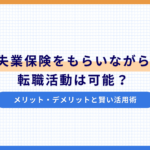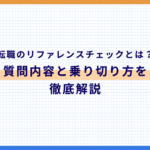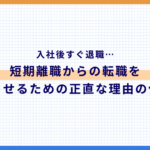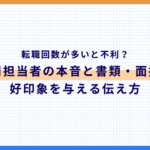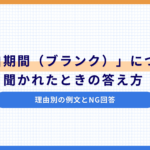面接で希望年収を聞かれたとき、『高く言って落とされたらどうしよう…』『でも安く言って後悔したくない…』と板挟みになっていませんか?
初めての転職なら、なおさら不安ですよね。
実は私自身、年収交渉を戦略的に行ったことで、給料を2倍以上にアップさせた経験があります。しかし、そこに至るまでには大きな失敗もありました。
新卒で入社した会社から初めて転職しようとした際、年収交渉の知識が全くなく、自分の市場価値も分からずに100社以上に応募しては落ちる日々…。当時は年収交渉どころではありませんでした。
その失敗経験から転職エージェントの重要性を痛感し、プロの力を借りて2回目の転職に挑戦。結果、スムーズな選考と戦略的な交渉で、満足のいく年収アップを実現できたのです。
そんな私のリアルな経験から導き出した、面接で希望年収をスマートに伝える方法と、年収交渉を成功させるベストなタイミングを、具体的な例文付きで徹底解説します。
きっと、あなたも自信を持って希望年収を伝えられるようになり、後悔しない転職を実現できます。
目次
そもそも企業はなぜ希望年収を聞くのか?3つの意図

まず、なぜ企業が面接で希望年収を質問するのか、その意図を理解しておきましょう。相手の意図が分かれば、適切な回答が見えてきます。
意図1:候補者の金銭感覚と自己評価を知りたい
希望年収の金額は、あなたが自身のスキルや経験を客観的にどう評価しているかを示す指標になります。
市場価値から大きく外れた金額を提示してしまうと、「自己分析ができていない」「金銭感覚がズレている」といったネガティブな印象を与えかねません。
意図2:自社の給与水準とマッチするか確認したい
企業には役職や等級に応じた給与テーブル(給与規定)が存在します。採用担当者は、あなたの希望年収が自社の給与テーブルの範囲内に収まるかを確認しています。
あまりに希望額とかけ離れている場合、採用してもミスマッチが起こる可能性が高いため、選考の早い段階で見極めたいと考えているのです。
意図3:入社意欲の高さを測りたい
希望年収の回答は、入社意欲を測るための一つの材料にもなります。
例えば、「給与が第一です」という姿勢が強く出すぎると、「他の会社からもっと良い条件が出たらすぐに辞めてしまうのでは?」と懸念される可能性があります。一方で、あまりに無頓着な回答も「本当に入社したいのかな?」と意欲を疑われる原因になります。
面接で希望年収を伝える前の必須準備3ステップ
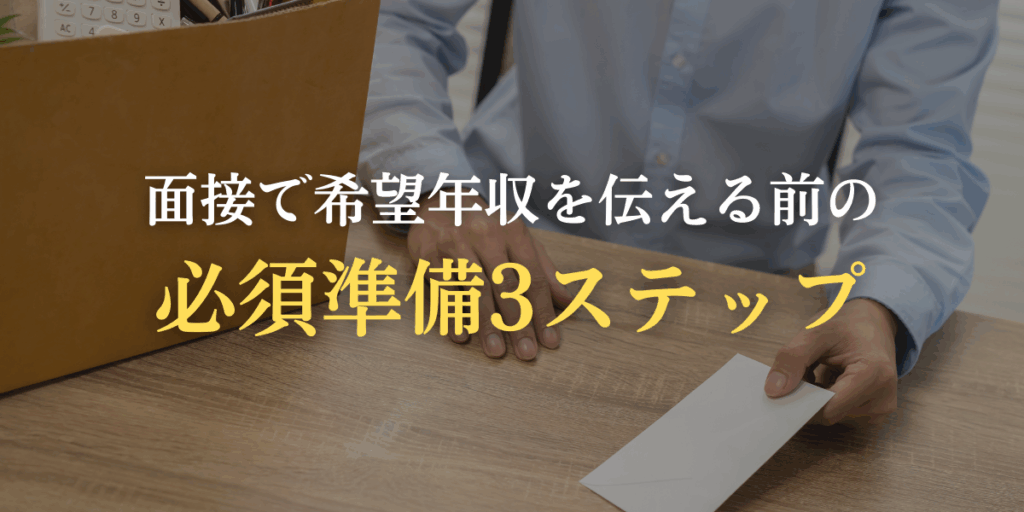
「じゃあ、具体的にいくらって言えばいいの?」と焦る前に、必ずやっておくべき3つの準備があります。この準備が、交渉成功の鍵を握ります。
ステップ1:自分の「最低希望年収」と「理想年収」を決める
まずは、自分の中で2つの基準額を設定しましょう。
- 最低希望年収(譲れないライン):これ以下の年収なら転職しない、と決められる最低限の金額。現職の年収や生活費から算出します。
- 理想年収(目標ライン):スキルや経験を正当に評価してもらえた場合に実現したい、理想的な金額。
この2つの軸を持つことで、交渉の際に冷静な判断が下せるようになります。
ステップ2:客観的なデータで自分の「市場価値」を把握する
自分だけの感覚で希望額を決めるのは危険です。客観的なデータに基づいて、自分の市場価値を把握しましょう。
- 公的機関の統計データを確認する:
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」などで、同年代・同業種・同学歴の平均年収を調べてみましょう。 - 転職サイトの年収診断ツールを使う:
いくつかの転職サイトが無料で提供している年収診断ツールを利用し、自分の経歴から算出される想定年収を確認します。 - 転職エージェントに相談する:
これが最も確実で効果的な方法です。転職エージェントは、常に最新の採用市場の動向や、非公開の年収データを把握しています。客観的な視点であなたの適正年収を算出し、交渉のサポートまでしてくれます。
ステップ3:希望年収の「根拠」を言語化する
なぜその年収を希望するのか、具体的な根拠を説明できるように準備しておくことが非常に重要です。
根拠の例
- 現職での実績(例:〇〇のプロジェクトを成功させ、売上を前年比120%に向上させた経験)
- 保有しているスキルや資格(例:〇〇の資格を保有しており、貴社の業務で即戦力として貢献できる)
- 現職の年収(例:現職では年収〇〇万円をいただいており、同等以上を希望いたします)
根拠を明確にすることで、あなたの希望に説得力が生まれ、採用担当者も納得しやすくなります。
【例文あり】面接での希望年収のスマートな答え方4パターン

準備が整ったら、いよいよ実践です。状況別に使える4つの回答パターンを例文とともに紹介します。
パターン1:「現職の年収」をベースに伝える回答
最も堅実で一般的な伝え方です。現職の年収を基準に、少し上乗せした金額を希望するパターンです。
例文
「現職では年収〇〇万円をいただいております。これまでの経験やスキルを活かし、貴社に貢献したいと考えておりますので、現職の年収を考慮の上、〇〇万円以上を希望いたします。」
ポイント:「以上」と付けることで、交渉の余地を残すのがポイントです。
パターン2:「希望額」を具体的に伝える回答
自分の市場価値に自信があり、明確な希望額がある場合に有効な伝え方です。
例文
「はい、〇〇万円を希望しております。現職で培った〇〇のスキルや、〇〇という実績を活かし、貴社の〇〇という分野で貢献できると考えているためです。」
ポイント:必ず希望額の根拠をセットで伝えましょう。なぜその金額が妥当だと考えているのかを論理的に説明することが重要です。
パターン3:「御社の規定に従います」と委ねる回答
未経験職種への転職や、自分の市場価値に自信がない場合に使える回答です。ただし、伝え方には注意が必要です。
良い例文
「現職の年収は〇〇万円です。選考を通して私のスキルや経験を正当に評価していただいた上で、貴社の給与規定に従いご提示いただけますと幸いです。」
悪い例文
「特に希望はありません。御社の規定に従います。」
ポイント:ただ委ねるのではなく、「現職の年収」を伝えた上で、「評価していただいた上で」という一言を添えるのが重要です。これにより、主体性がない、意欲が低いといったマイナスな印象を避けることができます。
パターン4:【最終手段】「希望年収はありますか?」と逆質問する
一次面接など、選考の早い段階で聞かれた場合に使えるテクニックです。
例文
「ありがとうございます。差し支えなければ、今回募集されているポジションの想定年収レンジをお伺いしてもよろしいでしょうか?」
ポイント:企業の想定年収を聞き出すことで、その後の回答を調整しやすくなります。ただし、多用すると「答えたくないのかな?」と思われる可能性もあるため、最終手段と考えましょう。
これはNG!評価を下げてしまう希望年収の伝え方3選
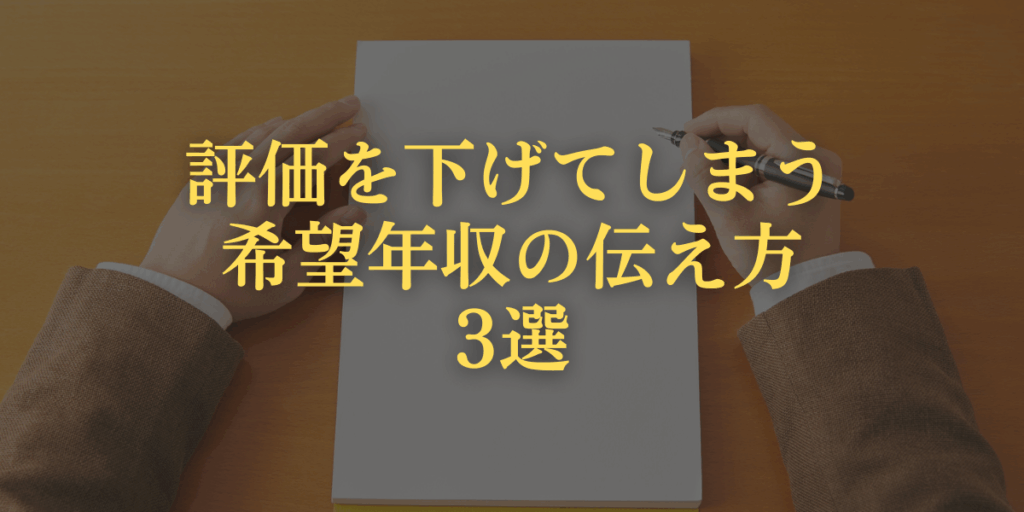
良かれと思って伝えたことが、逆に評価を下げてしまうこともあります。以下の3つのNG例には注意してください。
NG例1:根拠なく高すぎる金額を伝える
市場価値から大きくかけ離れた希望額を伝えると、「自己分析ができていない」「常識がない」と判断され、即不採用につながる可能性があります。
NG例2:希望額を「〇〇万円~〇〇万円」と幅を持たせる
「〇〇万円から〇〇万円くらいで…」のように幅を持たせた伝え方は、優柔不断な印象を与えます。また、企業側はほぼ確実に低い方の金額で検討するため、自分にとって不利になります。希望額は具体的な数字で伝えましょう。
NG例3:給与のことばかり質問する
もちろん年収は重要ですが、面接の場で給与に関する質問ばかりするのはNGです。 「この人はお金にしか興味がないのでは?」「仕事内容への関心は薄いのでは?」と、入社意欲を疑われてしまいます。
年収交渉に最適なタイミングは「内定後」一択!

希望年収を「伝える」ことと、「交渉する」ことはフェーズが異なります。年収交渉に最も適したタイミングは、ずばり「内定通知後〜内定承諾前」です。
なぜ面接の場での交渉は避けるべきなのか?
面接の段階では、企業はまだあなたを採用するかどうかを決めかねています。その段階で年収交渉を切り出すと、「条件ばかり気にする人だ」という印象を与え、選考自体が不利になるリスクがあります。
内定通知後〜承諾前の「オファー面談」が勝負の時
内定が出たということは、企業が「あなたに入社してほしい」と評価した証拠です。このタイミングであれば、対等な立場で交渉を進めることができます。 多くの場合、内定通知後に待遇などをすり合わせる「オファー面談」が設定されます。ここが年収交渉の最大のチャンスです。
【体験談】私が年収交渉で失敗しなかった理由
冒頭でお話しした通り、私は転職エージェントを活用したことで年収を2倍以上にアップさせることができました。その最大の理由は、年収交渉をすべてプロに任せたからです。
一度目の転職活動では、自分で企業と直接やり取りしていたため、お金の話を切り出すタイミングや伝え方に悩み、結局言い出せないまま…ということが多々ありました。
しかし二度目の転職では、担当のキャリアアドバイザーが私の希望と市場価値を把握した上で、企業側と巧みに交渉してくれたのです。結果、自分では言い出せなかったような希望額をはるかに超える条件を引き出してくれました。
【プロに任せる】年収交渉が不安なら転職エージェントを使わない手はない
もしあなたが年収交渉に少しでも不安を感じるなら、転職エージェントの利用を強くおすすめします。利用はすべて無料ですし、得られるメリットは計り知れません。
年収交渉をエージェントに任せる3つのメリット
- 聞きにくいことをすべて代行してくれる
自分では直接言いにくい年収や条件の話も、エージェントが第三者の立場から客観的に、かつ戦略的に企業へ伝えてくれます。心理的な負担がゼロになるのは大きなメリットです。 - 企業の給与水準を把握しているため、的確な交渉が可能
エージェントは、紹介先企業の給与テーブルや過去の採用実績を熟知しています。そのため、無謀な交渉ではなく、実現可能な範囲での最大値を狙った的確な交渉ができます。 - 過去の転職者の年収実績から交渉材料を提示してくれる
「同じような経歴の〇〇さんは、年収〇〇万円で入社しています」といった具体的な実績を元に交渉してくれるため、企業側の納得感も高まり、交渉が成功しやすくなります。
【20代・未経験に強い】年収アップを目指すなら登録必須のエージェント
「どのエージェントを選べばいいかわからない」という方のために、特に20代の初めての転職やキャリアチェンジに強く、年収交渉の実績も豊富なエージェントを紹介します。
【PR】
20代の転職・就職を全面サポート【Re就活エージェント】

私が特におすすめしたいのが、20代専門で実績No.1の「Re就活エージェント」です。
私自身、一度目の転職でキャリアチェンジに苦労した経験がありますが、
Re就活エージェントのような20代特化のサービスは、未経験でも挑戦できる求人が豊富で、サポートも手厚いのが特徴です。
特に、連絡ツールがLINEなので、忙しい中でも気軽に相談できるのが嬉しいポイント。初めての転職で不安な20代の方には、心強い味方になってくれるはずです。
もちろん、転職エージェントは担当者との相性も重要です。自分に合った担当者を見つけるためにも、2〜3社のエージェントに登録し、比較検討することをおすすめします。
| エージェント名 | 特徴 |
|---|---|
| Re就活エージェント | 20代登録比率No.1!未経験・キャリアチェンジに強く、LINEで気軽に相談できるのが魅力。初めての転職に最適。 |
| UZUZ第二新卒 | 第二新卒に特化。元既卒・第二新卒のカウンセラーが多く、親身なサポートが評判。入社後の定着率93.6%と高い。 |
| 第二新卒エージェントneo | 18歳~28歳まで幅広く対応。1人あたり平均10時間の手厚いサポートで、書類作成から面接対策まで徹底的に支援。 |
▼より詳しい転職エージェントの情報についてはこちらの記事を参考に
まとめ|自信を持って希望年収を伝えて、後悔しない転職を!
今回は、面接での希望年収の伝え方と交渉のタイミングについて解説しました。
この記事のポイント
- 事前準備が9割:「最低/理想年収」「市場価値」「根拠」を明確にしておく。
- 伝え方が重要:具体的な金額と根拠をセットで、自信を持って伝える。
- 交渉のタイミングは「内定後」:焦って面接で交渉するのはNG。
- 不安ならプロを頼る:転職エージェントを使えば、年収交渉の成功率が格段にアップする。
年収は、あなたのスキルや経験に対する正当な評価であり、今後のモチベーションや生活に直結する重要な要素です。 正しい知識を身につけ、戦略的に準備をすれば、希望の年収を実現することは決して難しくありません。
この記事が、あなたの後悔しない転職活動の一助となれば幸いです。
【期間限定】転職の無料相談しませんか?
「自分に合う仕事がわからない…」
「面接や書類でいつも落ちてしまう…」
そんな悩みを抱えていませんか?
今なら、私の公式LINEを追加するだけで、転職の無料相談を受け付けています。
さらに、友だち追加してくれた方限定で、転職活動のすべてが分かる『転職パーフェクトブック』を無料でプレゼント中!

後悔しない転職のために、まずは情報収集から始めてみませんか?

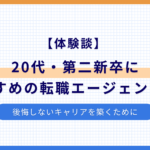


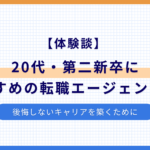

-150x150.png)